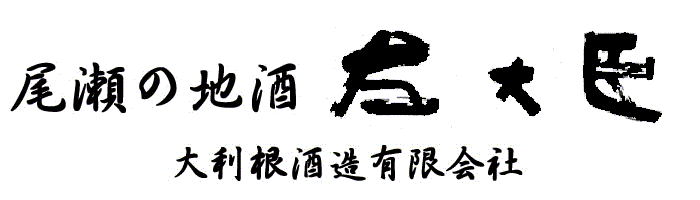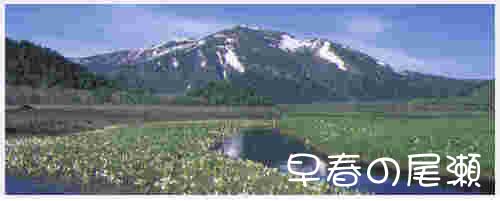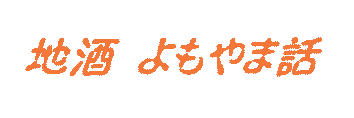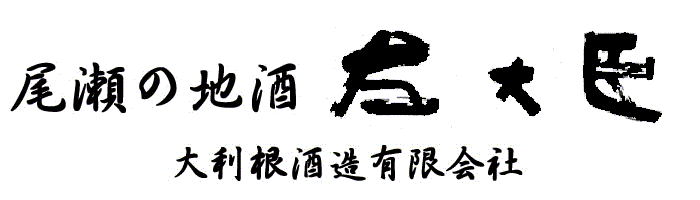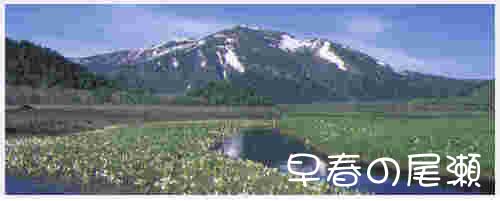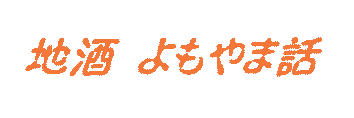|

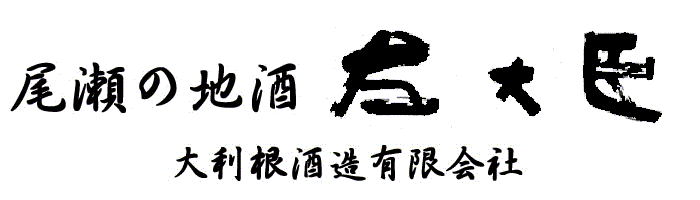

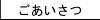
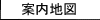
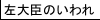
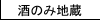
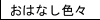
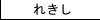
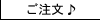

    
  ほーむ ほーむ
|
|
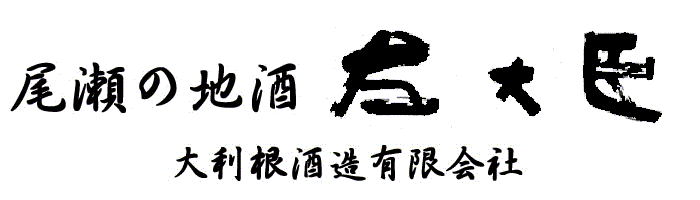 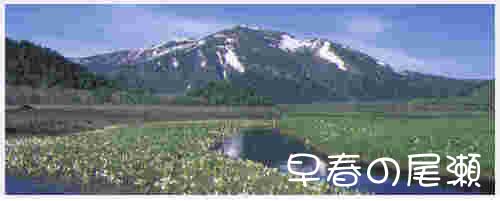
<
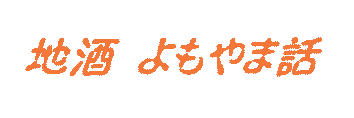
暮らしの中の日本酒 (1999.7.17掲載)
今でこそ日本酒の製造は「酒屋」と決まっているが、大昔酒は漬け物を漬けるように各家庭で造られていた。そのころの酒はどぶろくだが、みそ汁の味が家によって異なるように、それぞれの家で造られる酒の味も当然違っていたようだ。貴重な米を潰した酒だから、そうそう今のように気軽には呑めなかったと思うが、機会あるごとに「酒を呑む」慣習は今と変わらなかったろう。
さていつの頃からか、個人の酒造りが集団行為に変わり、ある程度の量産が可能になると、特定の業者として確立していった。これが酒屋の始まりである。元々は地域の酒を代表して醸す、と言った所だろうか。その後、長い年月の間に酒造りにも何度かの技術革新がなされ、特定業者のみの特殊技術として変化を遂げていった。
また、貯蔵方法の進展と海運の発達とで遠距離輸送が可能になり、遠方の酒も運ばれるようになっていった。貯蔵方法で革新的なのは、かなり早い時期に「火入れ」という殺菌方法が確立していた事である。
フランスのワイン醸造の歴史の中で、腐造防止の低温殺菌法が考案される約300年も前に、日本ではそれが確立され、実践されていたと言う。事実、室町時代の記録に火入れ作業の記録が残っている。また、陸運から海運へと輸送手段が変わると大量の酒が輸送できるようになり、江戸の新川土手には灘や伏見から運ばれた「富士見酒」を扱う酒問屋の蔵が連立していたそうだ。
そう言った中でも、大消費地以外や輸送に不便な地域では、その土地の酒の味が根付き、今なお地酒の味として多く残り知られている。特殊な例では神事用として少量の酒造りが許可されている神社があり、そこでしか味わえない独特などぶろくが信者に振る舞われるという。
私の暮らす利根沼田地方にも戦前は二十数場の藏元があったそうだ。それぞれの石高(製造数量)はまちまちであったろうが、当時の少ない人口比で見るとかなり多い数だと思う。機械のない時代なので、当然手造りの少量生産であったろうが、この広くない地域の中で「それぞれの味」を醸し出していた事に何とも興味をそそられる。
古来、酒はその土地で出来た米と、その土地の水とで造られた。山や木々、土や空気が育んだ自然の恵みを、人間の蓄積された知恵により酒に変えてきた。そして土地土地にそれぞれの味わいや異なった文化があるように、その土地の気候風土や水質、自然環境などによってそれぞれ酒の味わいも変わってくる。現在は何処でも、何でも手に入る時代ではあるが、その土地を訪ねて初めて本当の味わいを知ると言う事もあるのではないだろうか。
私たちの暮らしの中に浸透している酒。現在の身の回りの細かなところを見直してみると、色々なところで酒が登場しているのに改めて気づく。
今宵の盃には、本来どんな意味合いがあるのだろう。こんな事を考えてみるのもまた楽しい。
☆昔の酒造り
☆日本酒の効用
☆くらしのなかの酒
☆神事と酒
☆暮らしの中の日本酒
☆國酒
|