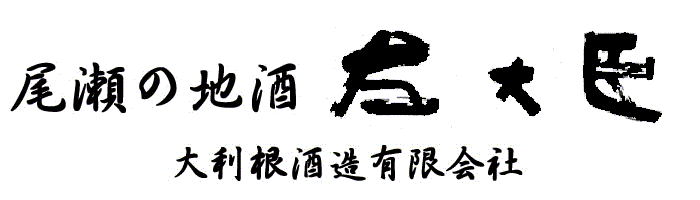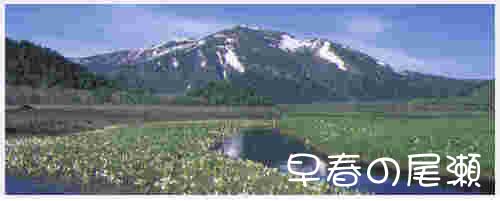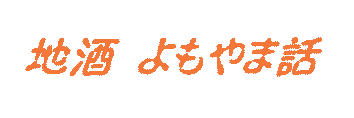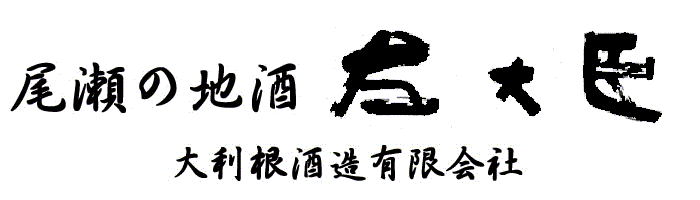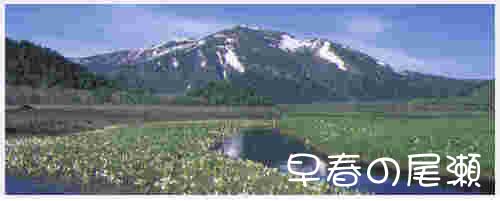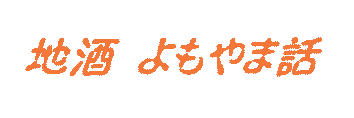|

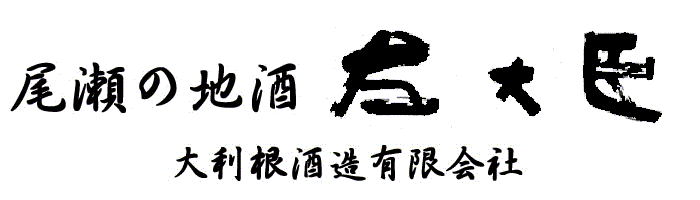

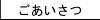
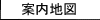
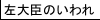
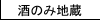
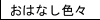
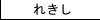
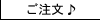

    
  ほーむ ほーむ
|
|
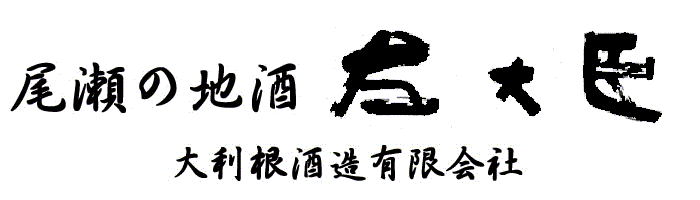 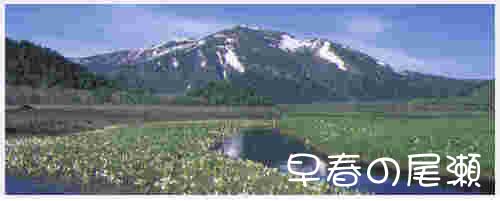
<
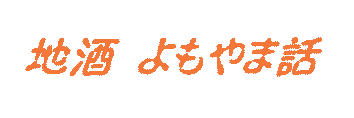
神事と酒 (1999.5.16掲載)
日本酒は、米の澱粉をベースにして麹による糖化と、併行して酵母がアルコール発酵を行って醸成される。だがこのような原理を、大昔の人達が知る由も無かったろう。
「神が造りたもうた酒」と言う言葉があるが、古来日本酒の製成は不思議な力によるものと考えられていた。 そこで、神と酒のつながりを考えてみた。古代の酔いを考えると、その現象こそ神の作用そのものであり、酒を呑んで酔うことが、すなわち神に近寄る手段であるという基本的な発想があったようだ。
こういう考えから、日本酒はまず神に供え、それから人が呑む。神にまず御神酒をと言う習わしが、今でも続いている。たとえばお祭りで
御神酒をいただく。もちろん酔いを求めて呑むわけだが、享楽の為の酔いではなく、より神に近づく為の手段として呑まれる。酒は古来神聖なものだったようである。現在では、科学的な考えが進み、神の存在は薄らいだとはいえ、習慣として神と酒は今でも充分に結びついている。
さて、いつ頃のことか定かではないが、日本固有と言われる「贈答思想」の発生はどうやら酒から来ているらしい。
大昔、まだ酒屋がなかった頃は、各家庭で酒が造られた。 各自の醸造法だから当然味も違ってくる。心をこめて醸した酒、これを贈ったのが贈答品のルーツと言う。こうした習慣から、やがて酒に肴を添えるようになり、生でなく保存に耐え得る「のしたアワビ」を添えるようになった。これが現在の「のし」の起源と言われている。現在でも、贈り物に「のし」をつけるが、自分が心をこめて醸した酒である、と言う心を表す意味があるそうだ。したがってもらう方は決して断れないわけで、相手に贈る場合の「のし」にはこんな意味がある。
こう言う例は世界にも類がなく、酒が人と人との関係を深く結びつけている。そしてそこには常に神が媒体として存在するという考え方である。その名残りが、現在でも折に触れて盃を傾けたり、宴を開いたりと言う事になるのだろうか。同じ瓶の酒を酌み交わす事で、気持ちの解放と接点を求め、お互いの理解を願うわけである。
さて、既婚の方は経験されたと思うが、 結婚式の時に神事として執り行う「三三九度の盃」と「親族固めの盃」。これも、同じ瓶の酒を共に分かち合い、より深い絆の証を永久に結び、人と人の関係を高めると言う意味合いがある。
日本では古くから神の存在を常に考えてきた。こう言った、神様を崇拝する慣習の中に、実は自然に対する神聖さや、尊さ、感謝の気持ちが込められているように思う。こう言った思いがやがて連帯意識に変わり、お互いの確認事項として、酒を酌み交わすようになったのだろう。
酒宴の席も、こんな故事を考えながら楽しんではいかがだろう。
今も、昔も酒を酌み交わすことの意味合いにかわりは無いようだ。
☆昔の酒造り
☆日本酒の効用
☆くらしのなかの酒
☆神事と酒
☆暮らしの中の日本酒
☆國酒
|