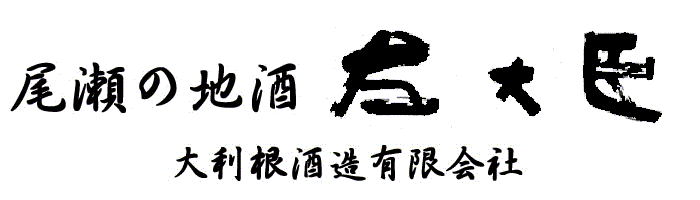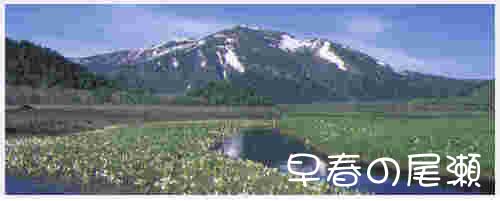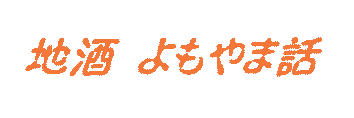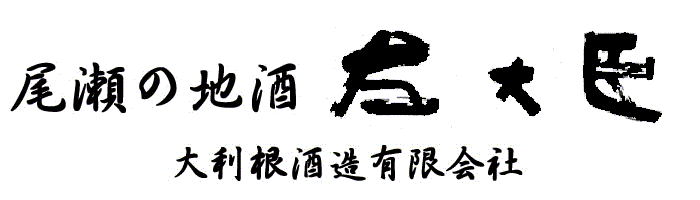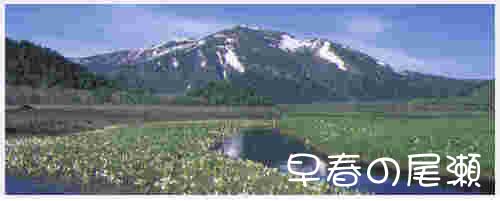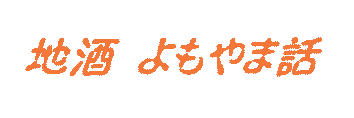|

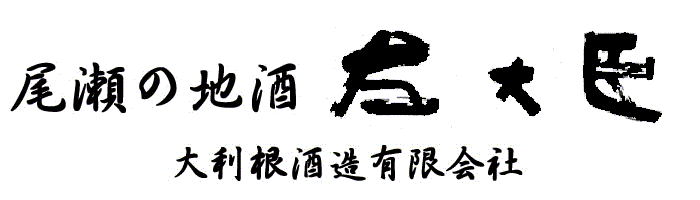

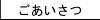
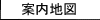
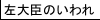
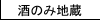
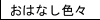
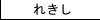
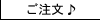

    
  ほーむ ほーむ
|
|
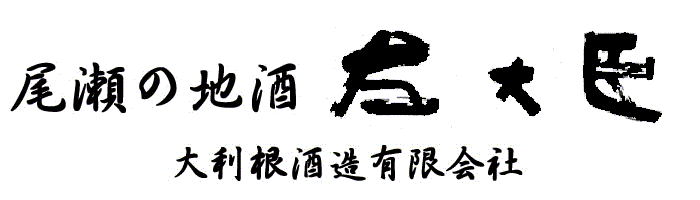 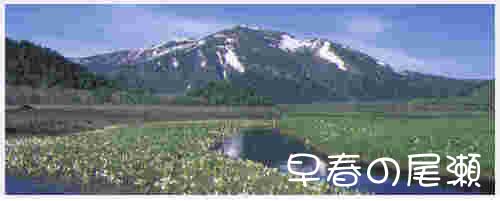
<
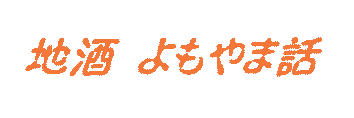
くらしの中の酒 (1999.3.24掲載)
花見の季節である。桜の開花とともに各地で酒宴が催される。この「花見」、どうやら日本独自のものらしく、外国人には珍しい習慣と見えるようである。
それでは、いつ頃から花見が始まったのだろう。
聞くところによると、桜はもともとは田の御神木であったらしい。桜の咲く頃になると、水も温み籾蒔きが始まる。田の神様がその時期を知らせるために桜の木に座り花を咲かせる、「田神降憑坐座」。
神(さ)の座(くら)わる所、だそうである。(「さ」は神霊感を意味する音で神を表す。)。神様のおかげで豊かに稔った米を酒に醸して供える。その御神酒を直会(なほらい)として戴く習慣が「花見」のはじまりかもしれない。昔から桜は、お百姓さんにとって尊い木だと聞いている。こんな所にも「神様とお酒」の関係が伺える。
日本には花見に限らず、古くから様々な宴があった。御正月の御屠蘇に始まり雪を眺めての雪見酒・桃の節句は桃酒・花見を終えると端午の節句に菖蒲酒・重陽の節句(9/9)には月見酒と、まだまだ沢山あるが季節や自然環境に合わせて酒宴を楽しんでいたようだ。
数年前機会があり京都の円通寺と言う寺に立ち寄った。枯山水の庭園を手前に、三部屋続きの大座敷からの展望は見事であった。比叡山を背景に人工建造物が全く見あたらないのだ。説明によると「自然界の背景を十分活かした景色造りを借景と言う。」そうである。これだけですばらしい眺めなのに、さらに季節に応じて雪や月・花や雲が登場する。こんな眺めの中で呑む酒はどんな味わいだろう・・・・・・。
日本酒の造り方も、また呑み方も時代とともに変化を遂げてきている。昔は日本酒しかなかったから「酒」と言えば当然日本酒であり、その呑み方も色々と工夫されていた。平安時代には、すでにオンザロックがあったと言うし、室町時代には?酒競技が行われていた記録もある。
昔から生活に浸透していた酒にまつわる噺や唄が、数多く残っている。現在も、日本酒に関わる色々な話や行事が沢山あるが、その一方で世界中のリカーが所狭しと肩を並べている。居ながらにして世界中の文化の一面を味わえるのだから大変良いことではあるが、反面、日本酒ばなれが進んでいるとも言われている。
人それぞれだから何を嗜もうと一向にかまわないが、日本の國酒とも言われている日本酒のすばらしさをいま一度再確認してみたいものである。
元来、日本酒は素晴らしい効用を持っていて、昔から「百薬の長」と言われて来た。単に酔いを求める為だけでなく、適量であれば医薬的効果も多く備えている。又、地域性も非常に豊かで、各地で違った味わいが楽しめる。
水質だけでも酒質は変化するが、その土地の風土や気候によって出来る米も、酒の味わいも微妙に変わってくる。そして、世界に数少ない醸造法で造られる日本酒だからこそ、多くの微量成分が複雑に絡み合い微妙な味わいを醸し出している。
古来より培われ、國酒とも言われている日本酒。呑み方を一工夫すれば味わいもより一層増すであろう。
☆昔の酒造り
☆日本酒の効用
☆くらしのなかの酒
☆神事と酒
☆暮らしの中の日本酒
☆國酒
|