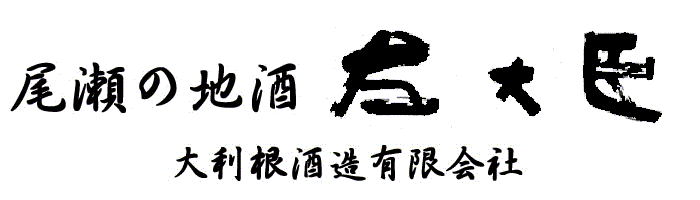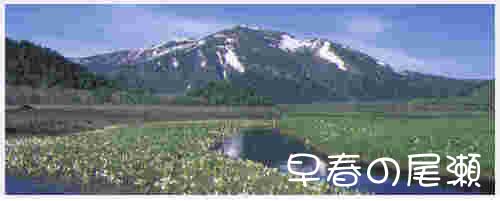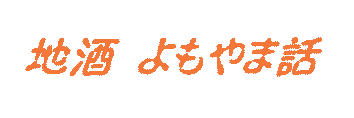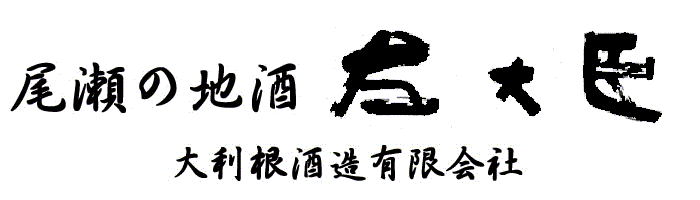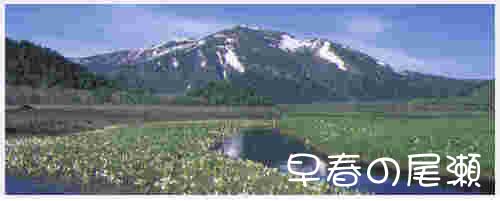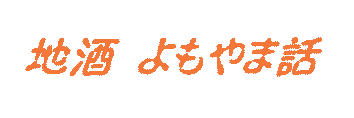|

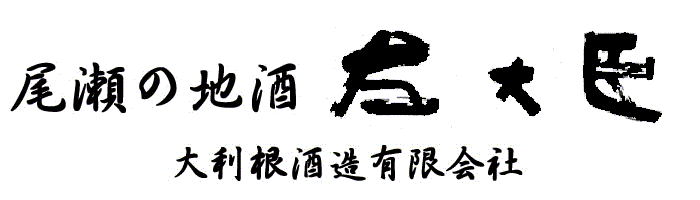

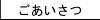
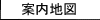
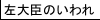
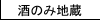
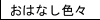
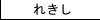
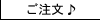

    
  ほーむ ほーむ
|
|
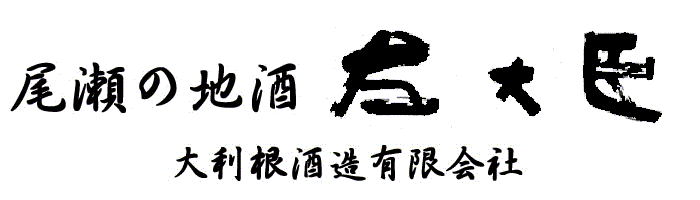 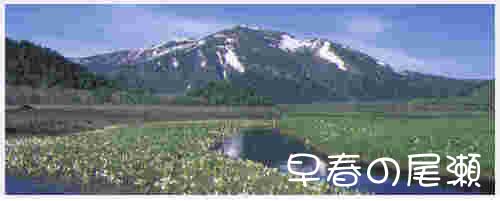
<
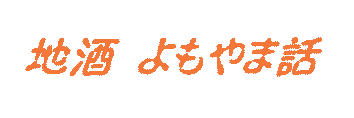
日本酒の効用(1999.1.23掲載)
近ごろ、発酵食品の効用が色々と取りざたされている。ことワインについてはメデイア的な効果もあり、体によいと評判のようだ。微量成分分析の技術が発達し、細かな効能も解るようになってきた。
では、日本酒はどうだろうか。 「日本酒の中にはアルコールのほか、有機酸、糖分、アミノ酸、ビタミン類など約105種類もの微量成分が含まれており、癌の発生リスクを軽減する効果が最近明確になっている。特に心筋梗塞、肝硬変、肝癌、消化器系癌の予防になる。」とのレポートを読んだ。大変喜ばしいことで、我々日本酒製造に従事するものにとっては朗報といえる。
昔から日本酒は「百薬の長」と言われている。個人差こそあれ適量適飲を守っていればまさに「百薬」であろう。 その定義は「医学的に安全な量を責任ある方法で飲む」と言うところだろうか。そのレポートの中に晩酌の定義も記してあった。「一日の仕事を終え、疲れを癒し、襟を外して心身をのびのびさせることを目的とした飲酒の習慣」だそうである。言いかえれば、「明日への活力を生み出すやすらぎのひととき」と言うことになる。
世界中には様々なお酒の飲み方があるが、日本では昔から夕食前に晩酌。そして必ず何かをつまむ、まさに食べながら呑むことになる。よく「酒呑みは左利き」と言われるが、右手に箸、左手に杯といった具合だ。
これに見られるように、日本酒は食中酒である。何か食べながら飲む、と言うことはアルコール消化の助けとなり、前記の効能も考えると体にも良い習慣で、燗であれ冷やであれ、楽しく適量であれば薬になりうる逸品かと思う。
さて、今でこそ色々な効用が解り、杯もすすみ話もはずむが、昔の人は知らず知らずに恩恵にあやかっていたことになる。もっとも、それも先人達が築きあげてきた文化の一面なのではあるが・・・
誰もが知っているように、日本酒は米から造られる。これはカビを使う醸造法が伝わって以来変わらないが、酒造りは色々な変化を遂げてきている。
口噛みの酒から、麹を使う醸造法に変わり、時とともに技術革新が成し遂げられた。奈良時代には古来の「濁酒」の他に、その上澄みだけをとった「上澄み酒」やもろみを濾した「澄酒」、その他にも「白酒」や「粉酒」と言った記録もある。そして驚くのは澄み酒の絞りかす、いわゆる今の「酒の粕」を湯に溶いた「糟湯酒」。これは酔うためだけでなく医薬的効果も求めて飲まれていたと言う。
また宮中の酒造りは種類も豊富で、すでに平安時代の「延喜式」には一五種類もの酒造法が記されているらしい。また、このころに「燗」、いわゆる酒を温める習慣が一般化したという。記録には延喜式の中に「煖酒器・煖御酒料」と言う文字が登場しているし、色々な古文に「燗・煖」の文字が伺える。
アルコールには元来血行を良くし、体を温める効果があるが、その酒を温めることにより代謝を効率良くする方法を確立していたことになる。
我々日本人の主食となり、古代より伝承されてきた命の源でもある米。その米の成分すべてが酒に溶け込み微妙な味わいや効能を生み出す。傾ける杯にこんな話を乗せると日本酒の深みも一入増すかと思う。
☆昔の酒造り
☆日本酒の効用
☆くらしのなかの酒
☆神事と酒
☆暮らしの中の日本酒
☆國酒
|