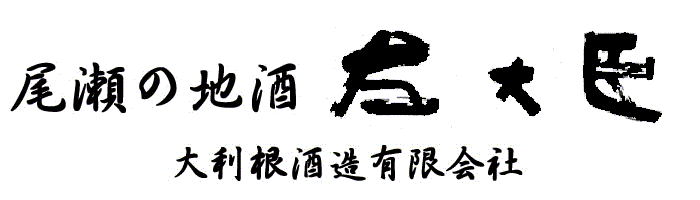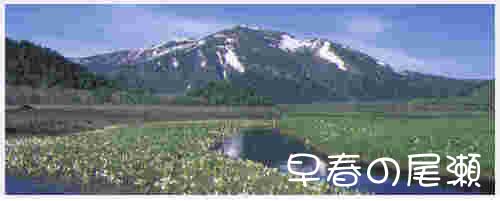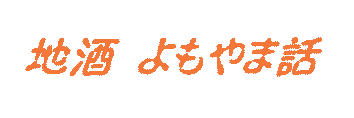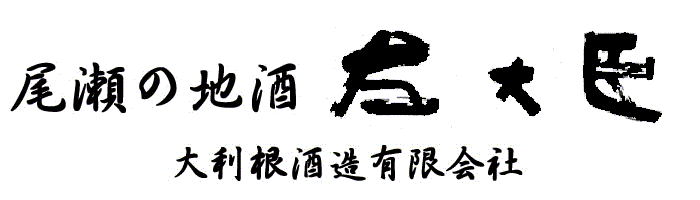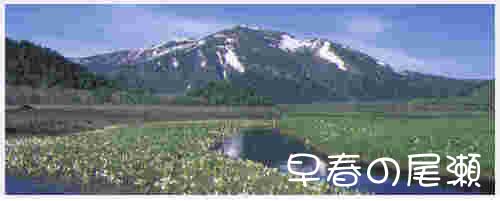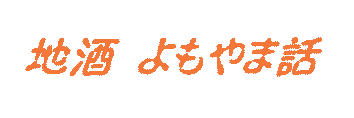|

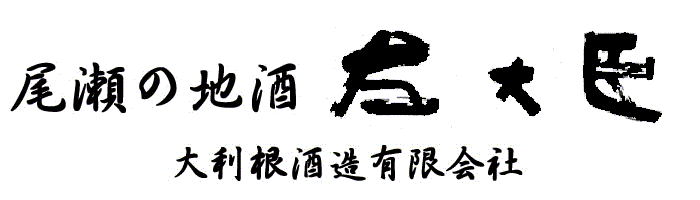

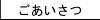
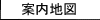
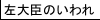
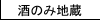
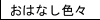
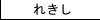
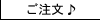

    
  ほーむ ほーむ
|
|
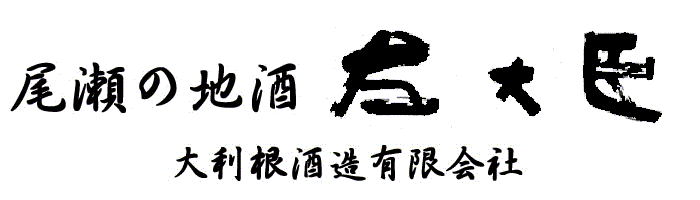 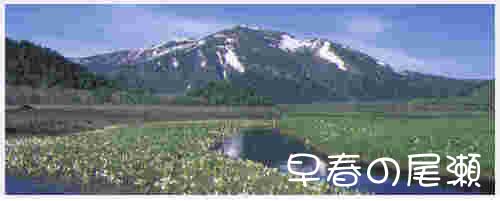
<
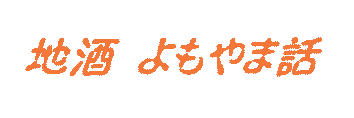
昔の酒造り (1998.11.23掲載)
弊社敷地内に松尾大明神(日本酒の守り神)の石宮がある。
刻まれた日付は「元文四年」と読めるから西暦一七〇〇年代の建立と思われる。その頃の酒造りはどのようになされていたのだろう。
子供の頃祖父から聞いた話によると、蔵人は春から秋にかけて本業の米作に従事し、冬は酒造りのための出稼ぎに出向く。
入蔵して最初外流し作り、麹室の断熱材(わら・もみがら等)の入れ替えから始まり、大釜のしつらえ、仕込桶等の洗浄と続く。電気も動力もなく、すべてが手作業に始まり、手作業に終わる。薪で湯を沸かし米を蒸かす。麹室に引き込み、大量の麹をつくる。本仕込みは六尺という大きな木桶で仕込む。
一番大変なのは温度管理だったろう。今のように温度調節機能が付いたタンクなどあるはずもなく、冷やすには水や雪を、暖めるには湯やむしろを使う。時計がないので唄で時を計る。夜も目が離せず交代で醪(もろみ)を見張り、皆造(かいぞう)迄には目立つ程体重が減ってしまう。
人力のみの世界なので当然沢山の人手が必要になった。杜氏を頭に年功序列が決まっており、一番下の「働き」は飯盛りも仕事のうちで、晩酌を楽しむ時間も無い程と聞かされた。今の機械管理醸造からは考えられない世界であったろう。一冬酒造りに従事すると言うことはこのように大変なことだったらしい。
では、そもそも酒はいつ頃からあったのだろうか。
最初に「酒」と言う文字が出てくるのは「記紀」である。その中に「八岐大蛇(やまたのおろち)を素戔鳴尊(すさのうのみこと)が退治する」くだりがあるが、文字としての最古の「酒」はこの物語に登場する。
ただしこの場合の酒は八塩折酒(やしおりのさけ)と記されているので、どうやら果実酒であったようだ。
歴史では中国大陸から米が伝わり、後にカビを用いた醸造法が伝わったと覚えているが、大陸の醸造法は色々なカビを使う。日本酒は麹かびのみを利用するもので、どうやら製法を模倣しているうちに日本独自の醸造法が確立されたようだ。それではその前はと言うと・・・もちろんあった。
そもそも「醸す」と言う言葉は、「はもす」。口ではもす、と言う意味らしく、当時では「くちはみのさけ」、穀物を口でかんで壺に蓄え酒にしたそうだ。今これを造って飲め、と言われても少々考えてしまうが、当時としてはこれが当たり前であったろうし、十分酒になったと思う。
日本酒の場合、平行復発行と言う複雑な発酵形態をとるのは知られているが、唾液中のアミラーゼが穀物の澱粉を糖に替える役割を果たしている。空気中に酵母は沢山浮遊しているので、温度が上手く行けば発酵する。今でも南方の原住民はとうもろこしやその他の穀類でこの「くちはみのさけ」を造り、神事や日常に用いていると聞く。
となると、日本酒は醸造酒なので、カビ醸造(こうじ)が普及してからが本来の日本酒と言う事になると思う。米は縄文後期に渡来したと言うが、カビを使った醸造はかなり時間が経過してからと言われている。中国に残っている魏志倭人伝(ぎしわじんでん)の中にも米を噛み酒にした、と記されている。
何れにしても、当時のアルコール度数はかなり低かったと思う。中には失敗して酒にならなかったものも多かったであろうし、当然濾過や精製技術は無かったろうからできた酒は「どぶろく」である。
この後、麹かびを利用した製法が広く普及し、平安時代の祝事に「黒貴・白貴をそなえ・・・」とあるので、その頃まで酒は一般には濾さずに呑まれていたようだ。濾された澄酒(すみざけ)については後でふれようと思うが、いずれにしても日本酒の歴史は遠く、そして私達の生活の中に深く根付いている。日常は勿論の事、祝事、清めと、事につけ酒が付いて回る。
大昔、初めて酒を口にした人たちは何を思ったであろうか。太古より培われ、暮らしの隅々まで浸透している日本酒、私はこの「日本酒文化」にとても興味をそそられる。
☆昔の酒造り
☆日本酒の効用
☆くらしのなかの酒
☆神事と酒
☆暮らしの中の日本酒
☆國酒
|